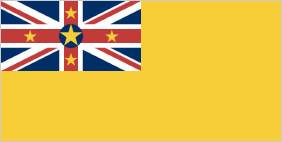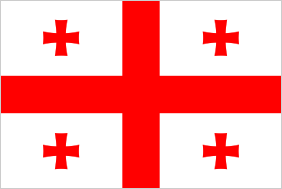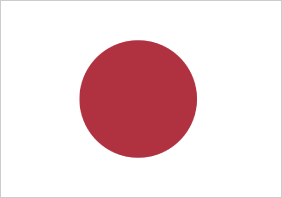日本経済新聞の「欧文異聞」と題するコラムはなかなか示唆に富む内容だ。
2013年3月24日付は西洋史家の樺山紘一先生が「シオニズムの始祖、ヘルツル」と題して、次のように書いておられる。
民族の居住の地を追われ、離散と流浪をしいられて2千年ちかく。ユダヤ人が、民族としての再結集と、故郷への帰還をもとめる運動は、シオニズムとよばれる。シオン、つまり栄光のエルサレムを奪回すること。
その思いが政治の顔貌をとるにいたるのは、19世紀の末年。提唱者は、テオドール・ヘルツルという若い作家である。
もっとも、ヨーロッパを中心とする各地のユダヤ人は、その運動にかなり懐疑的でもあった。なにせ、多くはそれぞれの地方社会への同化をすすめていたから。
1897年、スイスのバーゼルで第1回のシオニスト会議が開かれたとき、まだ方向は模索中。しかし、やがて雄弁のヘルツルの旗のもとで、ユダヤ人国家建設が、リアリティをもって語られるようになる。理想に燃えたのだ。
しかし、ヘルツルは現実の政治のもとで考えた。集住のための地をもとめて、イギリス・ロシア・トルコと、さまざまな国と掛けあった。アルゼンチンやウガンダなども候補にあがるほど。
著書『ユダヤ人国家』のタイトルから、ときに誤解もされるが、ヘルツルは純粋な民族国家を理想としたのではない。じつは、慎重に考えられた近代国家。国民の福祉をかかげ、宗教の自由、諸民族の穏和な共生も保障する。フランスのユートピア社会主義の空気になじんだというヘルツルは、まちがいなく近代政治思想の児(こ)であった。カリスマ指導者という、古めかしいイメージは覆る。
そうとなれば、パレスチナ帰還は、現住のアラブ人と、どんな関係を作りだすのかと問いたくなる。当時のヘルツルにあっては、まだ深刻な主題となっていなかったが。
シオニスト会議の始祖は、圧倒的な指導力を発揮した。到来したばかりの20世紀は、ユダヤ人にとって希望の時代になるはずだった。残念ながら、ヘルツルは、その行く末を見届けることなく、1904年、わずか44歳で生涯をとじた。

イスラエル建国の父テオドール・ヘルツル
古代のイスラエル、ユダ王国を滅ぼされて離散(ディアスポラ)したユダヤ人は、世界各地でしばしば差別や迫害にあうという苦難の道を歩んでいた。
1897年8月、スイスのバーゼルで第1回シオニスト会議が開かれた。イスラエル〈建国の父〉と呼ばれるヘルツルにより、「(心の故郷)シオンの山に帰ろう」という、シオニスト運動がスタートした。
イスラエルの国旗は、この会議の席上、やがてヘルツルの後継者となったウォルフソーンの次の提案で決まった。
「モーゼの時代からわれわれは自分の色、青と白を持っている。タリス(ユダヤ教の祈とう者の肩掛け)の色だ。この色で古代イスラエルの王者、ダビデ王の楯を描こう」。
第二次世界大戦中はユダヤ義勇軍の軍旗として使用され、1948年5月14日、パレスチナの地に共和国を樹立したイスラエルは、翌日からの第一次中東戦争のさなかの同年10月28日、国民評議会でこの国旗を制定した。「タビデの星旗」「六芒星旗」とも言われる。

イスラエル建国の父テオドール・ヘルツル
イスラエルの国旗は周囲のアラブ諸国の国旗には全く登場しない青が基調となっているところに、この国の中東における異分子的な、ユニークで複雑な立場が見える。